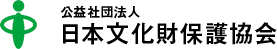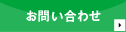横山 真 (株式会社ラング)
DX推進委員の横山です。
この10年ほどの間に、三次元計測システムは性能・価格のバリエーションを増やし、それを扱う私たちも意欲さえあればデータオペレーションのノウハウを容易に手にできる環境が整ってきました。文化財業界においても、三次元計測を積極的に進める研究者、調査機関・企業が増えているのを実感しており、これはとてもポジティブな動きだと考えています。
しかし「こうした三次元計測システムを導入したことで組織全体の生産性は向上しましたか?」という問いにYESと答える人は、それほど多くないのではないでしょうか。たとえば、人気のSfMは入力(撮影)こそ迅速に完了しますが、点群処理を経て必要なデータを取得するまでには多くの手間と時間を費やします。こうして得られた三次元データから二次元の線画に落とし込むことを最終目標とするならば、わざわざ三次元計測を行う意義が揺らぎ、結局のところ使い慣れたマコやディバイダーによる実測に戻ってしまった…という残念な事例も少なからず耳にします。このように期待通りの成果を出せない理由は、現状がまだ「デジタイゼーション」の段階、つまり「旧来のワークフローの上に新しい技術を走らせようとする状態」にあるからだと捉えています。
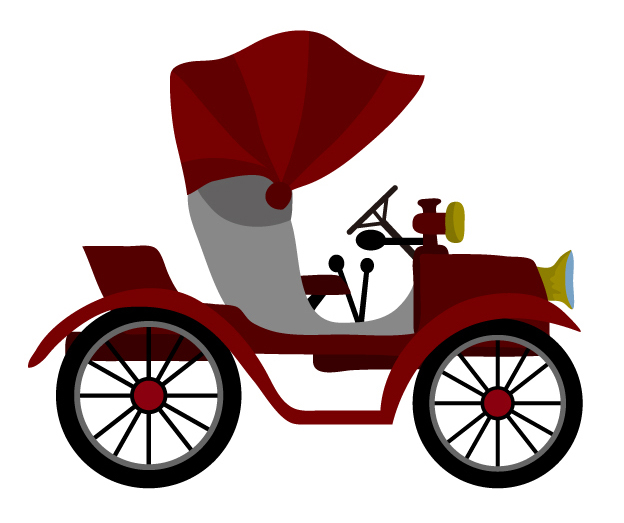
クラッシックカー イラストAC
ところで、日本の地に初めて自動車が上陸したのは19世紀末のことだったそうです。舗装道路もない時代には、初期の自動車は故障やパンクが頻発し、ガソリンスタンドもないため気軽に遠出することもできなかったと想像できます。「やっぱり馬が良いよね…」などと嘲笑されていたかもしれません。しかし現在、私たちが移動や物流において車社会の恩恵を当たり前のように享受できるのは、自動車自体の性能向上はもちろんのこと、車を走らせるための交通網、交通ルールなどの環境を社会全体で発展させてきたからです。文化財情報DXの現状は、このような社会の発達経緯に照らすならば、まさに黎明期と言えるでしょう。旧来の道に最新の技術を導入しようとする初期の自動車社会のように、まだ個別に試行錯誤している段階にあります。しかし、これは裏を返せば、今後の発展可能性が無限に広がっていることを示唆しています。
さて、DXにむけての取り組みは「新しい技術を走らせるための新しい環境をつくること」であると自分なりに理解しています。計測システムは、私たち利用者が特段の努力をしなくても、優秀なメーカー側が進化させてくれるものです。したがって、これからの主要な論点は、そうした計測システムを円滑に運用し、その能力を最大限に引き出すためのワークフロー、ルール、組織体制といった、社会全体で情報をつくり共有するための仕組みづくりに重点が置かれるものと思います。頭を柔らかくして生産的な議論を進めていければと思っています。